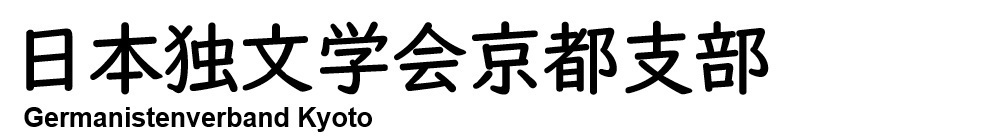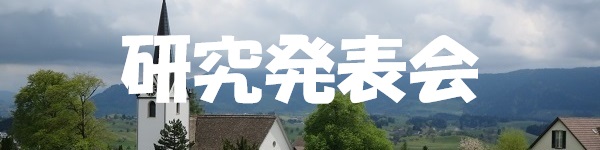研究発表会

チューリヒ近郊ヒルツェル村
研究発表会(2026年度春季)
詳細につきましては今しばらくお待ちください。
発表申し込み要領
研究発表会(春季・秋季の年2回開催)で口頭発表を希望される方は、発表を希望される年度・時期のおよそ6か月前(5月末もしくは11月末)までに、kyoto[AT]jgg.jp(京都支部アドレス)宛てに以下の項目についてメールでご連絡ください。
*@ は[AT]に置き換えてあります。
- お名前・所属
- ご希望の年度・時期
- 発表予定題目
- 内容要旨
(A4横書きで1200字以内、ドイツ語の場合は「執筆要領」1.2の規定に従って1枚以内)
これまでの研究発表会
※クリックするとプログラムが開きます。
- 久保 京花:
ベッティーナ・フォン・アルニムの書簡体小説について
- 中村 徳仁:
希望は発酵する――エルンスト・ブロッホにおける一つのモチーフについて――
- 大日向 悠河:
侵食される境界と恐怖小説を読む「読者」 ―― E. T. A. ホフマンの恐怖小説に関する物語構造的分析 ――
- 高橋 奏子:
小箱という希望 ―― アドルノにおける「新しいメルジーネ」 ――
- 武井 佑介:
日本語初級ドイツ語学習者がディスコースマーカーを必要とする会話場面の再考
- 下村 恭太:
ヴィラモヴィアン語の再帰代名詞の使用に関する一考察
- 木戸 吉則:
細やかなものの連合としての注意力 ― ベンヤミンのヴァレリー論より
- 武田 良材:
ナチス時代のスターリンによる粛清 ― ソ連登山界の成り立ちと悲劇
- 畑中 啓以力:
「オトフリートの福音書」における受動文 ― 格変化語尾を伴った過去分詞の使用条件に対する再検討 ―
- 中村 峻太郎:
ヴェルナー・ブロイニヒ『ルンメルプラッツ』における鉱山の表象
- 別府 陽子:
「芸術が奉仕する未来の共同体」を語るレーヴァーキューン ― トーマス・マン『ファウストゥス博士』詩論
- 作本 大祐:
アルザス語の母音連続にみられる子音生起現象の通時的複合性と“最適”な挿入子音の選択
- 山下 大輔:
語りの視点と承認の問題 ー フランツ・カフカ『歌姫ヨゼフィーネあるいはネズミ族』
- 林嵜 伸二:
フランツ・カフカの遺稿長編と短編の関係をめぐって ー『訴訟』と『流刑地にて』を中心に
- ポルドゥニャク エドワルド:
ヴィーラント初期メルヒェン作品における想像力論の展開
ー『ビリビンカー王子の物語』から『イドリスとツェニーデ』へ
- 小林 哲也:
怪物を読み解くこと ー W・ベンヤミンのカフカ論に寄せて ー
- 白坂 彩乃:
ムージル『特性のない男』における〈遙かな愛〉と兄妹愛
- 須藤 秀平:
18世紀の陰謀論
―反革命誌『オイデモニア』(1795-98)とその周辺における「真実」言説
- 中野 英莉子:
発話末のaberについての会話分析的考察
- 杉山 東洋:
旅路としてのモラトリアム ― シュティフターの『老独身者』について
- 松波 烈:
18世紀のフォールスメモリーシンドローム
―ヴィーラントの「ボニファーツ・シュライヒャー」序章を手がかりに
- 菅 利恵:
悲劇としての妊娠 ― レンツとゲーテにおける「子殺し女」のモチーフ
- 網谷 優司:
メランコリー論として見る初期フロイトの歩み ー「躁的防衛」から「投影性同一視としての喪の仕事」へー
- 下村 恭太:
ヴィラモヴィアン語における接続詞と人称代名詞との融合についての一考察
- 武井 佑介:
日本人ドイツ語学習者のディスコースマーカー使用傾向 ードイツ語会話内で出現する日本語DMs分析ー
- 中西 志門:
古英語と古ザクセン語における時を表す副詞的格の用法の比較-特にTagとNachtを中心に-
- 山口 知廣:
フランツ・カフカの作品における写真と映画
- 岡部 亜美:
コーパス調査に基づく姿勢動詞stehenとliegenの所在用法
- 籠 碧:
シュテファン・ツヴァイク『永遠の兄の目』における「孤独」のイメージについて
- 津田 拓人:
ムージルのクラーゲス受容における自然の表象
- 野添 聡:
ゴート語における動詞接頭辞ga- と分析的な完了形の比較研究
- 児玉 麻美:
レーナウと検閲ー―『ドン・ファン』における三月前期の時代徴標について
- 中祢 勝美:
バルバラの『ゲッティンゲン』(独語版,1967年)の成立に関わった人々
――W.ブランディンとM.シェクスを中心に――
- 橋本 紘樹:
エンツェンスベルガー『点字』における詩と社会の関係をめぐる問題
――テーオドル・アドルノへの批判的応答――
- 森口 大地:
『コリントの花嫁』における歪められた自己としてのヴァンパイア
- 高岡 智子:
コミュニスト・ナイト・フィーバー!
――東ドイツのディスコがつくるポップカルチャー――
- 牧野 広樹:
青年音楽運動における「聴覚/聴くこと」
- 川野 正嗣:
エルンスト・ユンガーと「森」の思想
- 鈴木 啓峻:
トーマス・マン『ヴァイマルのロッテ』における作者と主人公
- 佐藤 和弘:
Umwelt, Ökologie und Umweltbewusstsein ー―エコ言語学的アプローチ
- 寺澤 大奈:
マックス・フリッシュの戯曲『サンタクルス』――もう一度「生」を取り戻すために
- 細見 和之:
アドルノとツェラン――両者の往復書簡も手がかりとして
- 麻生 陽子:
ドロステ=ヒュルスホフの叙事詩『医者の遺言』における「作者性」の表現について
- 宇和川 雄:
ヴァルター・ベンヤミンにおける普遍史の理念
- 金子 哲太:
中高ドイツ語haben完了における視点について――Nibelungenliedに現れる例から
【シンポジウム】Was ist eigentlich die Originalität?
- 奥田 敏広:
ニーベルンゲン素材をめぐるワーグナーとフケー
- 松波 烈:
フケー『北方の英雄』の詩学
- Dieter Trauden:
Stoff und Rezeptionsgeschichte――Zur Nibelungensage und ihre Überlieferung
- 篠原 沙羅:
接触言語としてのトランシルヴァニア・ザクセン方言
- 益 敏郎:
ヘルダーリンと悲劇的英雄
- 國重 裕:
一人称の語りの可能性と限界――インゲボルク・バッハマンの小説を例に考える
- 勝山 紘子:
痛む身体の表象――オットー・ディックスの『戦争』を手掛かりに
- 西出 佳代:
ルクセンブルク語の動詞屈折におけるUmlautとAblaut
- 木村 英莉子:
話し言葉性についての一考察――疑問付加語句をもとに
- 吉田 千裕:
デーブリーン『たんぽぽ殺し』における病
- 松村 朋彦:
匂う/臭うドイツ文学――ティル・オイレンシュピーゲルからチェルノブイリまで
- 稲葉 瑛志:
前線兵士の知覚の変容――ヴァイマル期エルンスト・ユンガーにおける群集イメージ
- 河崎 靖:
ルーン文字の起源について
- 加賀 ラビ:
シュトルムの『グリースフース年代記』における主人公の人物像
- 紀之定 真理恵:
語り手に見る小説の構造――トーマス・マンの『ファウストゥス博士』をめぐって
- 大喜 祐太:
言語行為としての存在表現――es gibtの使用条件
- 西村 雅樹:
【講演】世紀末ウィーン文化の評論家ヘルマン・バール
- 中岡 翔子:
ゴーレム伝説とグスタフ・マイリンク『ゴーレム』
- 中村 直子:
不変化詞動詞(Partikelverb)における、一語書き・分かち書き
- 須藤 秀平:
アイヒェンドルフと「主観」の文学―民衆文学とのかかわりで
- 児玉 麻美:
失われた永遠の花――グラッベ『ドン・ファンとファウスト』における<求め得ぬもの>について
- 田原 憲和:
アントワーヌ・マイヤーがルクセンブルク語発展に及ぼした影響について
- 上村 昴史:
ドイツ・ルール地方の地域語における前置詞について
- 今井 敦:
F・G・ユンガー『技術の完成』における"Die totale Mobilmachung"の概念
- 山口 久美子:
ドイツ語におけるアクセントのない母音eの発音について――Schwaに関する音韻論的考察
ミニ・シンポジウム「啓蒙と反動の系譜」
- 1.青地 伯水:
占星術と天文学――グリルパルツァーの『ハプスブルクの兄弟争い』を手がかりに
- 2.川島 隆:
カフカ『あるアカデミーへの報告』とダーウィニズム
- 3.永畑 紗織:
ボブロフスキーにおける「反動」の系譜――ハーマン、ヘルダー、ロマン主義
- 須藤 秀平:
偶然性と人間――クライストにおける〈自由〉
- 鈴木 智:
自律的学習者の育成を目指したドイツ語の授業――読解ストラテジーを中心に
- 多田 哲:
16世紀ドイツ南西部における書記法の問題――Johhanes Brenzの宗教著作刊本を中心にして
- 藤原 美沙:
「現在」に影響を与える「子ども時代」の記憶――アイヒェンドルフの『大理石像』より
- 平野 嘉彦:
【講演】パウル・ツェラーン論――序
- 土屋 京子:
博物学の夢想と冒瀆――E.T.A.ホフマンの『ハイマトカーレ』と『蚤の親方』
- 筒井 友弥:
werden + Infinitifの用法に関する試論――要求行為を中心に
- 山崎 明日香:
ヴァーグナー『トリスタンとイゾルデ』における「傷」のモチーフ
- 薦田 奈美:
ドイツ語の意味変化に関する一考察――メタファーとメトニミーを中心に
- 千田 まや:
1920年代のトーマス・マンとユーゲント――『魔の山』から『ヨゼフ物語』へ
シンポジウム「啓蒙と反動の系譜」
- 序.青地伯水:
啓蒙と反動について
- 1.児玉麻美:
救済に内在する不安――啓蒙主義とファウスト作品
- 2.浅井麻帆:
リルケのゴシック空間について
- 3.青地伯水:
胎動する保守革命――リルケとフォルテ・クライス(1910-1915)の群像
- 吉村 淳一:
関係の形容詞の交換可能性について
ミニ・シンポジウム「世紀転換期のイディッシュ文化」
- 1.佐々木 茂人:
ユダヤ系ドイツ語作家が読んだイディッシュ文学――I. L. ペレツの作品とその翻訳をめぐって
- 2.西村 木綿:
思想としてのイディッシュ――「イディシズム」をめぐって
- 玉木 佳代子:
「創造的タスク」としてのプロジェクト学習――その理論と実践
- 廣川 智貴:
J.J.エンゲルの演劇論について
- 永畑 紗織:
真っ白な部屋のヘルミーネ――ヨハネス・ボブロフスキーの短編『立ち去りたい』についての試論
- 石澤 将人:
ニーチェとブルクハルトにおけるギリシア観と教養理念
- 齋藤 治之氏:
【講演】言語の体系における欠如と補充――gutの比較級、最上級はなぜbesser, bestなのか?
- 川西 孝男:
バイロイトとリヒャルト・ヴァーグナー
- 小林 哲也:
ベンヤミンの時間感覚
- 廣川 香織:
ヘルマン・ヘッセの小説における「顔」――『デミアン』から『シッダールタ』まで
- 伊藤 白:
トーマス・マン『欺かれた女』における女性像
- 羽根田 知子:
動詞のヴァレンツ――もとの動詞の補足語はどのように表現されるか
- 浅井 麻帆:
1890年代後半のウィーン分離派とゴットフリート・ゼンパー
- 谷口 栄一:
C.F.マイヤーの『説教壇から撃つ』における死と笑いについて
- 西井 美幸:
ゲオルゲ・クライスにおけるヘルダリン受容――グンドルフとベルトラムの場合
- 薦田 奈美:
意味変化現象について――認知言語学的視点から
- 樋口 梨々子:
音楽から文学へ――E.T.A.ホフマンの短編『リター・グルック』と『ドン・ファン』
- 青地 伯水:
エレクトラ狂乱――ギリシアの神々なき世界のホールマンスタール悲劇
- 寺井 紘子:
描き出される生――ホーフマンスタールのBilderをめぐって
- 坂本 建一郎:
印欧祖語動詞語根ueik-に基づく地名要素について
- 岡山 祐子:
ゲオルク・ビュヒナーの文学における革命と神の摂理
- 武田 良材:
ケステンの『ニュルンベルクの双子』におけるモラルの勝利
- 國重 裕:
非在の場所[ユートピア]としての故郷チェコ=スロヴァキア――亡命作家リブシェ・モニコヴァ
- 熊谷 哲哉:
光としての言葉――D・P・シュレーバーにおける自然科学と心霊学
- 林嵜 伸二:
ドイツ的な対立?――精神分析家Otto Grossにおけるdas Eigeneとdas Fremdeについて
- 青木 三陽:
宮廷叙事詩の伝統とヴォルフラムの『パルツィヴァール』
- 横道 誠:
ムージルにあって〈特性のない〉とは何であるか?
- 齋藤 治之:
ゲルマン語研究の地平線――中央アジア印欧言語との類似性
- 川島 隆:
ハイルマン中国訳詩集とカフカ
- 檜枝 陽一郎:
中低ドイツ語の西域における状況について
- 北岡 幸代:
ヴァルター・ラーテナウとユダヤ的なるもの――不安な知の発見
- 廣川 智貴:
語り手が語るもの――クライストの『チリの地震』
- Heike Pinnau-Sato:
Sind alternative Methoden in den Deutschunterricht integrierbar? Wenn, dann wie?
- 西江 秀三:
ドイツ語授業の動機づけの試み
- 安藤 知里:
京都大学におけるCALL授業の現状とマルチメディアCALL教材の開発
- 青地 伯水:
アイヒの「神学」における魔術的全一世界――ネオプラトニズムの影響下にある『ザベト』の考察
- 池田 晋也:
シュニッツラーにおける「劇場」
- 井原 聖:
ドイツ語の分離動詞構造の見直し
- 林 信長:
近代と現代の哲学的思考の分岐点としてのニーチェ「力への意志」――M.ハイデガーによるニーチェ読解を手引きとして
- 佐々木 茂人:
バル・コクバと「民謡の夕べ」――カフカの東方ユダヤ受容との関連で
- 吉村 淳一:
2格の修飾的機能について
- 中村 敦子:
都市市民文学としてのドイツ中世宗教劇
- 羽根田 知子:
中級文法における時制選択の問題――どこまで規範化できるか、あるいはすべきか
- 宮田 眞治:
跳躍としての〈かたち〉・亀裂としての〈かたち〉――ノヴァーリスにおけるFigurについて
- 菅 利恵:
父に葬られる娘――ヘッベルの『ユーリア』をめぐって
- 河崎 靖/フレデリック・クレインス:
【ミニ・シンポジウム】ゲルマンとラテンの間で――ベルギーの言語境界線
- 濱中 春:
革命の図像学――シラー『ヴィルヘルム・テル』
- 中村 直子:
正書法改革はどれだけ受け入れられたか?
- 奈倉 洋子:
グリムのユダヤ人像をめぐって