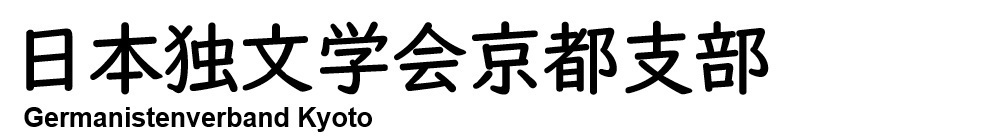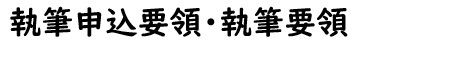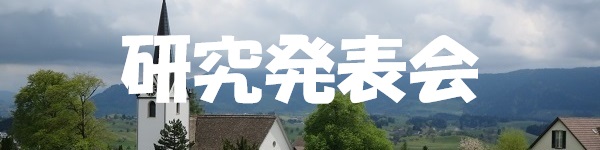『Germanistik Kyoto』

鴨川デルタ
最新号:第26号(2025)
目次
- 林 英哉:
規範への抵抗の物語
― テオドール・シュトルム『ある画家の仕事』における障害 ―
- 武田 良材:
ナチス時代のスターリンによる粛清
― ソ連登山界の成り立ちと悲劇 ―
- 下村 恭太:
ヴィラモヴィアン語における再帰代名詞の使用
― ポーランド語の影響による再帰代名詞の使用拡大 ―
投稿・執筆要領
※下の画像をクリックするとPDFファイルが開きます。<2025年度版>
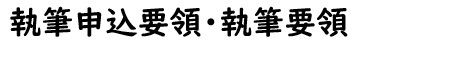
バックナンバー
※クリックすると目次が開きます。
- 児玉 麻美:
理想の劇場の創出を目指して
― グラッベの演劇理論における悲喜劇的要素について ―
- 吉田 千裕:
デーブリーン『ベルリン・アレクサンダー広場』における都市と人間の再生
- 高辻 正久:
第二次世界大戦後のトーマス・マンの中国に関する記述
- 須藤 秀平:
18 世紀の陰謀論
― 反革命誌『オイデモニア』(1795-98)における「真実」言説 ―
- 網谷 優司:
メランコリーの治癒に向けて
― 精神分析史における抗うつ剤としてのフモール ―
- 森口 大地:
〈吐き気〉を催させるヴァンパイア―ゲーテとE.T.A.ホフマンから抽出されるヴァンパイア像
- 飯島 雄太郎:
語り得ぬものとしての故郷
トーマス・ベルンハルト『行く』における引用による語りについて
- 武井 佑介:
初級ドイツ語学習者がディスコースマーカーを必要とする会話場面―ドイツ語会話におけるドイツ語・日本語ディスコースマーカーの使用場面と使用方法分析―
- 白坂 彩乃:
ヴァイニンガーとプラトン的な愛――『 性と性格』を中心に――
- 鈴木 啓峻:
ドミトリー・メレシコフスキーを読むトーマス・マン
――「 第三の国」における「エロス的禁欲」の位相をめぐって――
- 牧野 広樹:
沈黙するメデイア――クリスタ・ヴォルフ『メデイア さまざまな声』における語りと沈黙――
- 岡部 亜美:
姿勢動詞 stehen と liegen で建物の所在を表す用法に関するコーパス調査
- 児玉 麻美:
レーナウと検閲――『ドン・ファン』における三月前期の時代徴標について――
- 橋本 紘樹:
詩と社会をめぐるエンツェンスベルガーの問題圏、『点字』から『時刻表』へ――テーオドル・アドルノへの批判的応答――
- 牧野 広樹:
青年音楽運動における聴覚論
- 川野 正嗣:
エルンスト・ユンガーにおける「森」の思想――自由と抵抗の人間像
- 籠 碧:
アルフレート・デーブリーン『たんぽぽ殺し』と精神医学――理解できる狂人と理解できない健常者
- 稲葉 瑛志:
冷たさ、苦痛、有機的構成――1930年代初頭のエルンスト・ユンガーにおける「政治の美学化」言説について
- 益 敏郎:
ヘルダーリンと有罪なる英雄――『ソフォクレスの悲劇』における英雄的形象の変容をてがかりに
- 麻生 陽子:
三月前期の書く女たち――ドロステの文学的パノラマとしての『ペルデュー! あるいは出版人、詩人、そして文学かぶれの女たち』
- 西尾 宇広:
『壊れ甕』あるいは裁きの劇場――クライストの劇作家としての自己理解をめぐって
- 宇和川 雄:
ゲシュタルト論争――ベンヤミンのグンドルフ批判
- 稲葉 瑛志:
前線兵士の知覚の変容――ヴァイマル初期エルンスト・ユンガーの群集イメージ
- 熊谷 哲哉:
臓器移植と自己意識――ダーヴィット・ヴァーグナーの『生命』について
- DAIGI, Yuta:
Existenzkonstruktion als Sprechakt――Akzeptabilität der "es gibt"-Konstruktion
- 須藤 秀平:
アイヒェンドルフと「主観」の文学――歴史叙述における詩人の役割
- 麻生 陽子:
閾の存在としての女吸血鬼とジェンダー――ドロステ=ヒュルスホフの『ローデンシルト嬢』
- 林嵜 伸二:
フランツ・カフカのバベルの塔物語『都市の紋章』
- 上村 昂史:
ドイツ・ルール地方の地域語における前置詞について――融合形に関する一考察
- 藤原 美沙:
俗物と詩人を超えて――アイヒェンドルフの『のらくら者の生活から』における「子どもらしさ」の考察
- 山口 久美子:
ドイツ語におけるアクセントのない母音eの発音について――Schwaに関する音韻論的考察
- 今井 敦:
革命的ナショナリズムから技術批判へ――F・G・ユンガーの技術論(1)
- 須藤 秀平:
クライストにおける「自由なる魂」――『ヘルマンの戦い』を中心に
- 伊藤 白:
『ヨセフとその兄弟たち』の女性像――ムト・エム・エネトに描かれた自己像とナチス像
- 薦田 奈美:
メタファー・メトニミーと意味変化――gutとschönの意味変化を例として
- 児玉 麻美:
量られる知、危機への予兆――18世紀ファウスト劇における「警告の文字」のモチーフについて
- 林嵜 伸二:
フランツ・カフカのもう一つの<アメリカ>――インディアン像の変遷をてがかりに
- 千田 まや:
1920年代のトーマス・マンとユーゲント――『魔の山』から『ヨゼフ物語』へ
- 石澤 将人:
教養の故郷としてのギリシア――ニーチェとブルクハルトの教養理念
- 小林 哲也:
「純粋さ」と「純化」――『カール・クラウス』におけるベンヤミンの政治的姿勢
- NAGAHATA, Saori:
Hermine in einem ganz weißen Zimmer――Über Johannes Bobrowskis Erzählung „Ich will fortgehen“
- 川西 孝男:
バイロイトとリヒャルト・ヴァーグナー
- 熊谷 哲哉:
目的・進化・自由意志――シュレーバーにおける世界認識の問題
- 高野 佳代:
フランツ・カフカの「ユダヤ民族ホーム」支援とリリー・ブラウン回想録
- 佐々木 茂人:
「小国民の音楽、クレズマーと「発話旋律」
- 廣川 香織:
身体へのまなざし――ヘルマン・ヘッセの『湯治客』について
- 加賀 ラビ:
政治的アレゴリーとしてのトーマス・マンの小説『欺かれた女』
- 青地 伯水:
エレクトラの狂乱とディオニュソスの苦悩
- 伊藤 白:
インマ・スペールマンあるいはカーチャ・プリングスハイム――トーマス・マン『大公殿下』における女性像とユダヤ性
- 樋口 梨々子:
音楽から文学へ――E.T.A.ホフマンの短編『リター・グルック』と「ロマン主義的なるもの」
- 廣川 智貴:
詩人は病人か?――ゲーテ『トルクヴァート・タッソー』におけるメランコリーについて
- 青地 伯水:
まどろむ不変の定数――保守革命を介してのアイヒとナチスの親和性
- 川島 隆:
カフカ『徴兵』に描かれた異民族「通婚」の挫折――1920年の物語断片に見るロシア像とユダヤ人問題の接点から
- 寺井 紘子:
描き出される生――ホーフマンスタールの"Bilder"をめぐって
- 浅井 麻帆:
ウィーン分離派の建設費用から見えてくるもの――ルートヴィヒ・ヘヴェシのテクストを通して
- PINNAU, Heike:
Die Anthropozentrik der Sprache――aus ökolinguistischer Sicht
- 青木 三陽:
ハルトマンのアルトゥースロマンとヴォルフラムの『パルツィヴァール』――「彩りを添えられる」物語
- 佐々木 茂人:
カフカとイディッシュ語――カフカの講演における「ジャルゴン」という表現をめぐって
- 横道 誠:
ムージルがエレメント論を拡張する――受容されたマッハ思想から「培養液」の世界と「新しい人」まで
- 青地 伯水:
アイヒ詩学の転換――その政治的発言との関連
- 川島 隆:
漢詩を読むカフカ――『ある闘いの記録』における異性愛排除のテーマとの関連から
- 國重 裕:
「主婦」が書く小説――マルレーン・ハウスホーファー『屋根裏部屋』(1969)について
- 濱中 春:
メタ・イメージとテクスト――リヒテンベルクの『ホガース銅版画詳解』における画中画の解説について
- PINNAU, Heike:
Optimierung des DaF-Unterrichts durch den Einsatz von Elementen aus alternativen Unterrichtsmethoden――auf der Suche nach einem erweiterten Horizont für den DaF-Unterricht
- 青地 伯水:
エピファニーと強迫的自己認識過程――ホフマンスタールの『騎士物語』とアイヒの『もう一人の私』とにおけるドッペルゲンガーモティーフ
- 奥田 敏広:
トーマス・マンの『フリードリヒ』小説構想について――エロスとナショナリズム
- 村田 竜道:
ロシア軍将校としてのヨハン・ゴットフリート・ゾイメ――あるいはポーランド第2次分割の共犯者としてのゾイメ
- 中村 敦子:
都市と宗教劇――ドイツ中世宗教劇とその機能
- 佐々木 茂人:
「バル・コクバ」と「民謡の夕べ」――カフカの東方ユダヤ受容の背景をめぐって
- 菅 利恵:
父に葬られる娘――フリードリヒ・ヘッベルの『ユーリア』
- KAWASAKI, Yasushi:
Graphematische Untersuchungen zu den altsächsischen Heliand-Handschriften
- Scheiffele, Eberhard:
【書評】Yutaka Yamaguchi: Heinrich Mann Studien
- 飛鳥井 雅友:
抒情的自我――ベン以前、ベン以後
- 吉田 孝夫:
ローベルト・ヴァルザーと世界劇場――再話的文学の根底について
- 阿部 美規:
再帰代名詞sichの新しい配語法記述に向けて――現代ドイツ語のコーパスに基づいた分析
- 中村 雅美:
現代ドイツ語時制論における混乱とその原因について